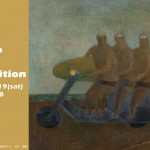7年ぶりという森直子さんの陶芸展が今日から。器だけでなく、篆刻や俳句も陶でという試みにー游ぶーと名付けた。しんにょうの「遊」とほぼ同じ意味だが、こちらの「游」には游永とか浮游とかさんずいならではの語感が。今回の仕事にはこちらの語がぴったりときたのだろう。
幅広い森さんの世界だが、陶芸の道では土ものを島田猛先生に、磁器を川崎忠夫先生について修めた本格派。大きい柄の蕪の器はたっぷりとして使い勝手がよさそうだ。色使いも品良く、食卓での出番が多いに違いないと思われる器の数々は毎回大人気という。茶道も嗜まれる方だけに、いいものを見てもいらっしゃるのだろう。絵付けの具合も心にくい。
また俳句の世界では中原道夫宗匠が主宰する「銀化」の中心メンバー・水内慶太師のもとで研鑽を積まれた。師直筆の「風呂敷に 月をつつみし 耳ふたつ 」という句を陶板にし、三歩下がった位置に自句「肩双べ 渉るポンヌフ 冬銀河」を並べた具合もよし。実家寒河江家の叔母さまとともに始めた俳句というが、打ち込んでこられた様子が思われる。
さらに陶印を彫り、押印して亡きお母様の形見の着物で表装した塩梅もまたただ人ではない。大正時代から昭和にかけて謳歌したであろう時代の名残を思わせる美しい意匠の着物である。傷んだところを外して布取りし表具されたこれらの軸は、また100年の命を得た。
「陶」という一つの素材を使って、今までご自身が打ち込んでこられた様々な世界を統合しようという試みはー「游ぶ」ーという一言にくくられ、涼しく立ちあらわれた。プロでもアマでもない、いわば「文人」のような自由な境地に遊ぶー森さんの美意識は着物の趣味にも表れ、京呉服の老舗「志ま亀」さんのご主人丹精のはんなりした型染めの着尺に、富本憲吉の陶印を描いた塩瀬の帯で出で立ってらした。陶印の柄という、珍しい帯の発想を、先代とご縁が深かった富本憲吉の印を展示した京都の美術館で得たという「志ま亀」のご主人もお見事なら、この展覧会にこの帯でと、躊躇いもなく購われた森さんも見事。
美意識というのは一朝一夕に培われるものではなく、着物ひとつのお見立てにも丁々発止のやり取りがあるときく。陶芸や俳句、茶道、篆刻など日本の文化に深く根ざした世界に遊んで来た森さんならではの「おこのみ」を展覧会を通して観させていただいた。
これを教養と呼ぶのだと思う。さらに楽しく游泳して、自由な文人魂を発揮してほしい、と願うや切。
森京子展
2002年、2005年と続けた森京子の三度目の個展が今日から。33歳の時に独立美術協会の会員に推挙され、以後着々と地歩を築いて来た森京子。変型の額から鉄のオブジェが飛び出したり、作品に色々な冒険を施してきたが、今展では身辺のものたちを軽いタッチで描いた。
 画廊全体を一枚のキャンバスに見立て、縦横に展示された作品たち。入口には画廊の模型が置かれ、タイトルと作品位置が示されている。模型の玄関から本物の画廊を覗く、という二重の構造が面白い仕掛けとなっている。
画廊全体を一枚のキャンバスに見立て、縦横に展示された作品たち。入口には画廊の模型が置かれ、タイトルと作品位置が示されている。模型の玄関から本物の画廊を覗く、という二重の構造が面白い仕掛けとなっている。
大作が並ぶ団体展では、寸分の隙もない完成度の高い作品を求められるため、個展では肩の力を抜いたスケッチ風の作品を並べたいという意図をもって制作されたものたちは、森京子の普段の生活のなかから抽出された。昨年から飼い始めたというシーズー犬の「チャイ」君や、ご夫君の彫刻が並ぶ玄関の風景など、身近なモチーフを中心に0号から、100号まで怒濤の31点が並ぶ画廊の一隅には、制作のもとになった画想のメモやら、エスキースやら、作品一歩手前の鉛筆デッサンやらコピーやらが、アトリエの壁のように展示されている。
普段、アトリエから出てこない「絵になる始め」の色々な資料とともに完成図をみるという試みだが、このなかには秘蔵の写真も含まれ、これら作品の卵のどれが孵化しどれが揺籃のなかなのかを探るのも楽しい。
普通の光景と見えつつ、異次元の世界へと誘う仕掛けは変わらぬまでも、葉山での暮らしが穏やかな光に包まれたものに違いないということだけはわかる。赤褐色の鉄さびの色調から明るい緑のバリエーションに変わり、不安や孤独の影は奥へ隠された。自分らしさというオリジナリティを求めていくうちに、一番大切な生活のありかに気がついたのかもしれない。
日々変わっていく自分、その有りどころが作品に反映されていくーだから、生きている作家には目が離せない。描く方も見る方も日々が真剣勝負だと思う次第。
越畑喜代美展ー京王百貨店にて開催
四度目の春の京王百貨店シリーズ開催中の越畑喜代美。以下、この展覧会のために賜った佐藤美術館学芸員・山川望氏の文章である。
日々の呼吸
確かにその絵は呼吸をしていた。
それはとても密かにおこなわれているらしい。だから絵の前では普段より少し目を凝らして耳を澄ますといい。そうして心穏やかに絵を見ていると、いつの間にか自分の気持ちがすっと軽くなったように感じた。その絵の作者である越畑さんご本人も当然そんな心地よさ、周囲にいつも人が集まる魅力を持っている。越畑さんは希有な眼を持つ人で、普通の人なら見逃してしまいそうな日々の機微をしっかりみつけてくる。きっと慌ただしい暮らしのなかにあっても、小さな幸福感をたくさん手にすることに長けているのだろう。このことは絵の世界まで繋がっていて、世界観の構成と無関係とは思えない。小さな幸福感を契機とする作品はそのひとつひとつが大切に描かれているに違いなく、そうでなければこの幸福感のお裾分けにあずかることは難しいはずなのだ。
そんな日本画家の手がける絵には、何代にも渡って大切にされてきた骨董品のような趣がある。流行とは無縁、派手さも前面にこそ感じられないが、絵肌から感じられる独特の暖かみ、じわじわと利いてくる味わいの深さはいまだ底をみせていない。今回の展示にも期待してしまう所以だ。
また、越畑喜代美のこんな文章も是非味わってほしい。
樹々の小枝から透ける空
こっそりポケットに入れて 連れて帰りたくなるような風景
ゆっくりと変って往く雲のかたち
風に乗る旅の仕度をしている草々の種
時の順番を律儀に守る 小さな虫たち
ガラス越しに のんびり並ぶ誰かのおみやげ
どうか私も仲間に入れてほしいと 焦がれてみるが
ちっぽけな私に 誰も気づきはしないだろう。
片思いの恋文のように スケッチしたり 絵にしてみたり。
今の気持ちを描いてみる。
季節の変わり目にうきうきするのは新たな出会いの予感と 再会の歓びがあるからなんだと思う。
明日吹く風のにおいを 今日も楽しみにしている。
Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20