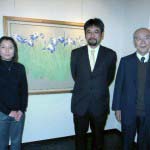当画廊初登場の牛尾卓巳のご紹介をする。
牛尾卓巳は1969年広島生まれ。1995年武蔵野美大大学院デザイン専攻を卒業すると、テキスタイルアート分野のコンクールや賞に出品し、ファイバーアーティストとして活躍を始める。在学中の個展をはじめに、主にフェルト素材をもちいたインスタレーションを発表、羊毛の縮絨がもたらす皮のような凝縮された肌合いや絞りによる形態の変容を作品化してきた。
「ひとがた」といえばいいのか、そのオブジェは人がまとう「衣」の形を造形するが、なかに「人」は不在である。その空虚感と、「衣」の妙な実在感が、不思議な磁場を空間に成立させていた。
そんなクールな作品を発表している牛尾卓巳だったが、その素材でマフラーを織っているという。暖かい羊毛を使いながら、あちこちに隙間があるその「役にたつんだかたたないんだかわからない」マフラーをみて一目で気に入った私は、是非にと個展を依頼したのだった。
思えば一目惚れした去年の黒羽よしえさんのフェルトの帽子に続き、羊ものの第二弾であるが、年に一度くらいは触れるものがやりたいと「手」がうずくのである。
「羊力」といみじくも題された今展だが、まさしく私が魅了されているのは、この「羊」の持つ力なのだろう。毛に縮絨を掛けると「布」に変化する。その魔法のような力は、洋の東西を問わず古来から人類を寒気から守って来た。その素材に魅せられ、新たに違う可能性を引き出そうとするのもまた人類である。
牛尾作品はこのフェルトに隙間を与えた。本来隙間なく繊維が密着し板状になるのがフェルトである。そこに穴をあけてレースのような装飾性を加味したのである。あまり寒いときにはこの隙間のあるマフラーはものの用に立ちそうではないように思える。が、用から離れた美の独立というほど、とんがってもいない。さりげなく空気のすきまを創り出す自由さがその本領だろう。
実際首の回りに巻いて見ると、思いがけずふんわりとやさしい感じでまとわりついてくる。隙間はフェルトの特徴ともいえる硬さを、たくみに柔らかさに変える装置でもあったのだ。織りや編みの風合いを残しながら縮絨する技術がどのくらい大変なものか、わたしにはわからない。だが、直接はだにふれる感じで作者が空気まで計算しながら、この柔らかさを醸し出しているのだ、ということは実感できた。
現在、女子美大と家政大、東京デザイナー学院で講師を勤める牛尾卓巳は、テキスタイルという専攻のため学生時代から今にいたるまで女性陣に囲まれて制作している。精緻で美しいのに甘さがない、彼の制作にむける真摯な姿勢は女子学生たちのいい刺激になっていることだろう。今展でもマフラーという、ありふれた素材にあらゆる可能性を織り込んでみせてくれた。その前衛性と、目立たぬように隠された抒情性を矛盾なく成立せしめているのは、ひとえに彼の賢さによる。
すきま風すら取り込んで、牛尾卓巳のマフラーは人を温めるのである。
平坂常弘展ーIWAMI ふるさとの色
平坂常弘が石見のふるさととともに銀座にやってきた。
1955年島根県浜田市三隅町に生まれた平坂さんは、’79年多摩美大・日本画科を卒業すると郷里に帰り起業、市会議員などを経て浜田市立石正美術館の館長として活躍されている。 仕事のかたわら再び絵筆をと思い立ったのは50代を目前にした頃ときく。思いがけぬ大病が、その契機となった。郷里の先輩画家・石本正先生のお近くにいて旺盛な制作意欲を目の当たりにしていた事も勿論あっただろう。繁忙な日々をぬうように再び制作を始め、画家復活ののろしは’06年銀座・文芸春秋画廊であげられた。
以後、長い空白を埋めるかのごとく怒濤の進軍、今年は故郷・浜田の草花舍ギャラリー、この度は当画廊で発表、さらに来春は京都のギャラリー蒼い風での個展と意欲をみせるのである。 一貫してテーマは「ふるさと」。自分を育み、今も日々を送るふるさとへの讃歌は尽きる事がない。今展の案内状の作品「初冬」は、秋の収穫のあわただしさを残す田の中の轍(わだち)とその水たまりに映る初冬の空を描いたもの。画面上部に小さく抜ける青空をもつこの大地は、営々と続く実りの象徴でありながら人の営為から離れて自然に立ち戻っていく。その一瞬の枯れ詫びた彩りを繊細にうつし取り、清澄な空へと解き放つ感性の奥底には詩がある。
日常の顔から画家の顔になる時、平坂さんの胸中には詩があふれているに違いない。「流(たび)」と題したスコットランド薊の作品には重層的な時間の流れが抒情的に描かれて秀逸だし、また「壊村」の壊れ行く家屋の壁にも草花を揺らす「風」にも、悠久の時間とともに、限りある命への愛惜がこめられている。
平坂さんにとっての詩はとは生と死を見つめた先にある余情なのではないか、と作品を見ながら思った。いわば燃え尽きたあとまだすっくと立つ生命力の美しさ、である。一瞬滅びとみえるなかに、命の力強さや真の骨格を見ようという意思を感じるのである。
みずからの母胎であるふるさとや親しいものの姿をかりて、生死を超えた普遍の時間を画面に刻もうとする平坂さんの仕事はこれからまたさらに充実の度合いを深めるであろう。そんな予感をはらんだ展覧会であった。
山田りえ展ー12度目の個展
深紅の薔薇の女王・山田りえが一年ぶりに登場した。越畑喜代美同様当画廊最長不倒距離を更新しつつ、デパートや画商さんの企画展に引っ張りだこの人気画家とあいなった。多忙からか一昨年昨年は腰痛に苦しんだが、養生の甲斐あったか今年は快調。繊細なタッチを画面に加えつつ山田りえらしい切れを見せてくれた。 山田りえは1961年京都に生まれ、1983年多摩美大日本画科を卒業すると神奈川県立西湘高校に奉職。勤務の傍ら制作をはじめる。その後約十年二足のわらじをはくが、画作に専心するため職を持し旺盛に発表を始め今に至る。 12回目を数える今展では秋草や山野草など自宅の庭で育てた花々を描いた。初回から数年は個展時期が春だったせいか春の花々のきらびやかな色彩が豪華な展覧会だったが、近年は調整上秋の時期のせいか、比較的秘めやかな彩りの印象だった。荒々しいまでにエネルギッシュなタッチから、画面の隅々まで気配の行き届いた調子に変化し、堂々の風格を湛えるようになってきた。 金箔地に赤の薔薇と緑の葉叢という取り合わせは、ともすると下品になりがちな派手な取り合わせだが、今展の山田りえの真骨頂はいとも簡単にそれをすっきりとモダンに変えたことだ。その間然するところのない切れ味は誰も真似出来ないところ。かつて暑苦しいほどに濃密だった作品の空気が、クールに張りつめたものに変化して我々に迫ってくる。今展では小品ながら「あけび」の空間処理に奥行きと成熟をみた。 画家も刻々と変化する。毎年見逃せないその変化は一年では気がつかないが十年の歩みを振り返ると歴然となる。当画廊の十年選手は、それぞれにその跡を見せて来た。無我夢中で制作に追われながら残した軌跡はある時は停滞しある時は飛躍する。年々歳々発見し挑みながら山田りえの嚢中にはまだまだ画想の種が詰まっている。それをどう育んでいくのかがこれからの仕事だ。 画家の師の加山又造氏は、なんどもその画風を変えている。ただそのどれをとっても加山又造の仕事である。先達の画家の残した足跡は大きな道標だ。ある時は風景、ある時は裸婦、ある時は花鳥、ある時は水墨とその豊かな才を惜しまなかった。もちろん師は師、であるがどこかでそのDNAを受け継ぐ資質が山田りえにはある。いよいよ50代をま間近に控えてこれからどういう画世界を紡いでいくのか、かたずをのんで見守りたい。
矢島史織展スタート
矢島史織が茅野から新作をさげてやってきた。 1979年長野県茅野市生まれの矢島は、2005年多摩美大大学院日本画科卒の新鋭。在学中に福知山市佐藤太清美術賞展入選、第三回トリエンナーレ豊橋・星野眞吾賞展などに入選を重ね、若手ながら着々と道を切り拓いてきた。
当画廊とは、2005年の卒展と同時に行ったグループ「七味展」がご縁のはじまりで、2007年春には銀座で個展デビュー。以後、銀座スルガ台画廊、横浜そごう、神戸そごうなどで発表を続けてきている。 初個展のおりには、木漏れ日シリーズからガラスに映る陰影を描いた作品に移行する時期だった。柔らかな光が白い壁や道に複雑な模様を描くさまを、自分の心情と重ねてあらわした作品で透明な詩情が長く印象に残った。
今展では、ガラスシリーズとともに、風化したサンゴの陰影を描いた作品が初めて登場。新たなモチーフと出会った喜びを感じさせてくれた。 個展に先駆けて、地元紙「信濃毎日新聞」に月二回連載されているH氏賞受賞の詩人・杉本真維子さんの詩とエッセーに絵を寄せるというコラボをしている矢島が、杉本さんの文章にある中唐の詩人・李賀の「恨血千年土中碧」という詞に反応して起きた銀化が作品「積層の断片」と「積層の風景」だ。
恨みを残して死んだ人の血は土中で千年たつとエメラルドに結晶する、という詞のイメージを白化したサンゴに置き換え、表面の凹凸に色々な表情をあたえた。サンゴももとはサンゴ虫の集積、長い時間をかけて育ちやがて死んで風化する。永遠のような時間を刻んだサンゴを拾い、その表面をかくことで堆積した時間にまで分け入ろうと欲っしたのか、白い陰影はあたかも抽象形のように我々に薄い残像をのこすばかりだ。その儚さを追い像を結ぼうと心が動くーそこにある単純な凹凸になんと多くの風景が隠されているのだろう。集積は時間ばかりではなく記憶も包括するのだった。
また沖縄の那覇の海と網走の灯台を封じ込めたガラスのコップの作品は、画廊内に新しい天体図を展開してみせてくれた。コップになみなみとつがれて溢れ出す瞬間の水面は、緊張と解放のドラマを宿す壺中の天でもある。この小さな天体のなかで、一瞬は永遠となる。 矢島はこの一瞬のコレクターであり、その集積を作品としているのであろう。
阿部清子展ー結婚
阿部清子の四度目の個展が今日から。阿部は1970年東京に生まれ、独学で日本画の技法を習得、1996年臥龍桜日本画大賞展に出品した後、南京、島原、淡路島、沖縄など各地に移住し、その場所の人々を描くことを通じてコミュニケーションの手だてとしてきた。
期間の長短はあろうが、その間多くの出会いと別れを繰り返してきたことは想像に難くない。2005年東京に戻ったのち、佐藤美術館でのグループ展「万様種子展」に出品した作品を一見して、そのひりひりするような孤独を思わずにはいられなかった。
縁あって2006年から当画廊で毎年個展を続け、冒頭に書いたように今年で4回目となった。今展のテーマは「結婚」。第一回は粗い岩絵具で描き込んだ作品が多かったが、第二回の「劇場」、第三回の「多感のすすめ」と回を重ねるにつれ和紙の余白を生かしたドローイング風の作品が多くなる。その墨作品について最近「趣味の水墨画」に寄稿した阿部の文章があるので少し長くなるが引用する。
墨との対話 私にとっての墨の魅力は、「ニュートラル」だということだろうか。発色も色味も動きも線も、描き手の意思や品性、性格までもありのままに映し出す。そこが怖さでもあり、震えるような喜びを感じるところでもある。
描くことは、筆をいれる側の私の画材への一方的な支配や制圧ではなく、あくまでも対話である。まるで意思があるかのように自由に動き展開する墨に対し、「ああそうですか、そういきますか…」と驚きを感じつつ受け入れ、「しかしここはどうしてもこういたしますよ」と応じつつ通す。そんなやりとりの中で、自分を知り、対象への理解と興味を深めていく。人としての日々もそんなものかもしれない。(中略)生きることと連動した描くという行為の良き伴侶としての墨が静かに、時に劇的に私を導くような予感がしている。今後も自分と制作に正直に、学びと対話を重ねていきたい。阿部清子阿部が制作にあたって一番気をつけているのは、自分がどこにいきたいのかをしっかり自覚しているかどうかだという。ゆえにタイトルをはっきり決めてから、そこに向かって走りはじめるのだそうだ。今展の「結婚」も上記の理由から構想された。
小説に「私小説」という一体があるが、阿部の作画もそれに似て作者自身の生活感情を披瀝しながら突き進む。ときに生すぎて、驚くほどであるが、余計なフィルターがない分ストレートに伝えたいことが胸に届く。「これっていいの?」と自問自答しながら作品を一巡する。個展空間があたかも劇場に見立てられたかのように、それぞれの作品の目線がからみ、結婚の諸相が浮かび上がる仕掛けだ。
「私絵画」という言い方は適切ではないかもしれないが、墨の一線がまるで果たし合いの刃のように、紙と自身に引き下ろされた現場に立ち会っていると、いささか厳粛な気分になってくる。このような「生々しさ」は、現代人が意図的に隠そうとしてきた何かに触れるものであり、知性や揶揄のカーテンで遮ってきたものである。そのほぼ忘れかけたものーいわば「生きる熱情」のようなものを、いきなりカーテンを引いて見せたのだから衝撃的だ。
本人はおそらく満身創痍ながら、これしか出来ない道を歩んでいる。いや、求めている。ためらい傷とおぼしき墨の線も見受けられる中、迷わず進んで闇から「玉」を探し、光のなかに出てくる日を楽しみに待つとしよう。
桐生好展ー拾い物
当画廊では9年ぶり4度目の桐生好展が始まった。幾多の試練を乗り越え、自分の足でしっかり地面に立っている姿はまことに凛々しいもの
。 桐生好は1972年、長野県飯田市生まれ。91年に上京し、美術の専門学校で抽象造形を学んでいる。グループ展などを経て、98年に当画廊で初個展。以後、99,00年と続けたのち、現代美術の方向を目差し02年にはマキイマサルファインアーツで発表を始める。前後して郷里・飯田に帰郷、当地にて美術研究所を開催し地元や名古屋でも旺盛な活動を展開し、今に至っている。
上京の折り折りに近況を聞いてはいたが、美術を柱に生活を組み立てていくのは東京でも至難のこと、まして飯田で果敢に挑んでいる姿は見事というしかないと、陰ながら声援を送らせてもらっていた。
今回の個展は、大海にでた稚魚が大きくなって生まれた川に戻るがごとし、と喜んでいたが以下のステイトメントを読んで更にその成長を知る事となった。
今回の桐生好展は、昨年に続いて「拾い物」をテーマにしております。絵を描くために特別に用意したモチーフではなく、私の身辺に落ちていたものらです。
私の過去の展覧会は抽象画を中心に発表しておりましたが、最近は物を「見て描く」というごく単純な行為に充足感を得ております。対象物を見れば見るほど興味が湧き「これをなんとか表現したい」という気持ちに駆り立てられます。トンボのモチーフは、アトリエに三年間ほど放置されていたもので、ミイラのようになってしまいましたが、今でもその羽の精緻さには舌を巻きます。 近年の表現の世界は、多彩かつ難解さを極めております。私はその中でもう一度この単純な表現方法を見直し再挑戦したいと考えております。
桐生好 桐生が美術研究所の先生の紹介で、画廊に登場したのはたしか24才くらいだったろうか。少女めいた長い三つ編みが印象的だったが、もう三十代半ばときく。その三つ編みは今も健在で、髪の毛の先はちょうど腰ぐらいの位置でペットのようにまとわりついている。 この間、日々制作に没頭していたと思われる桐生が、抽象から具象へと変遷を重ねる経過について、今は述べない。心にある何かをどういう風に表現するかはその時々だからだ。ただ、頭や心が空っぽになった時に、外から贈り物のように何かが入ってくる。それが、桐生のいう「拾い物」なのだろう。自然のすぐ近くにいて、自然に気がつかないのが我々だ。その恩恵物は、目が開いた人にだけみえるもの。
ようやく当たり前のすごさに気がついた桐生に、自然の摂理は造形の不思議を教えた。これは今後、また抽象にもどるにしても大きな制作の手がかりになるだろう。
今展では、研究所の教え子で美大生となった方々もお祝いに駆けつけてくれた。また、普段配達に来てすぐ帰る宅急便のおにいさんが、絵に目をとめて「いいですね」と感想を。画廊始まって以来の言葉に私までうれしくなったことを言い添えておこう。
武井好之展ー沖縄百景・那覇リウボウ
武井好之展が沖縄リウボウデパートで始まった。
沖縄百景と銘打っての第1弾で、二十余景を描いている。2003年、初めて沖縄を取材した折りに出会った環礁を描いた4メートルの大作を始め、主に沖縄本島の各地に取材した力作の数々に、会場を訪れるご見物衆は驚きを隠せない様子だ。
日本画というジャンルの絵画をほとんど目にする機会がない沖縄の人々にとって、岩絵の具の透明感は不思議な質感らしい。
ほぼ岩絵の具の宣教師となった武井好之は、今回画材店・ウエマツ社長上田さんのご協力を得て沖縄用のグルーを開発してもらった。高温多湿の風土に合う膠の開発は沖縄に日本画を普及するにあたっての急務だった。武井の要望に応えて上田さんはでんぷん由来のかびないグルーを開発、今展の作品はすべてこれを使用している。
また、会期中の二日間別会場で岩絵の具講習会を開催し、日本画の楽しさに触れてもらおうと生徒も募っている。この教室が二度三度繰り返されるなかで、地元の方々に浸透していってほしいという武井の願いがいつの日か叶えられるよう心から祈るものである。
25日にはテレビ沖縄のニュースで今展の模様が放映され、27日には地元ラジオ局タイフーンFMのマジカルミステリーツァーに出演、楽しいオンエアとなった。この模様はポッドキャストで聞けるとのことなので是非武井のホンワカトークを聞いていただきたい。
今展は31日まで沖縄県那覇のリウボウ美術サロンで開催されている。武井と柴田によるどすこい夏場所はまだまだ続く。
渡辺夏子初個展
渡辺夏子は1983年千葉県市川生まれ。東京造形大学デザイン科出身ながら、日本画を志しこつこつ独学、初個展の運びになった。
仕事先の先輩の紹介で、悦子画廊で月一回開催している夜間デッサン会に参加し、一年以上になる。熱心に通うなぁと思っていたら、いつの間にか作品を描きためていたらしい。
趣味のダイビングで沖縄や奄美、伊豆、八丈島などに通ううち、あちこちの魚さんたちと馴染みになったらしい。聞けばお母様の実家のある佐渡で小さい頃から海で遊んでいたとか。今展ではその魚と花を組み合わせた楽しい作品たちを発表した。
デザイン科を選んだのは何故?と聞いたところ、日本の美術は空間や建築など生活に密着して育まれたものが多いので、そういう事がやりたかったとのこと。確かに琳派などは意匠のなかから生まれたもの。 気がつけば、好きなものは全部日本画の中にあった、という。金箔のなかで自在に泳ぎ回る南海の魚たちが添えられた花たちと戯れる図は、実際にはあり得ないことながら不思議なリアリティをもち、画面上にふくらみを与えている。
奄美のご縁で田中一村記念・奄美を描く美術展に二度入賞し、その地の方々にも可愛がられているという。
まだ25才。その前途には果てしない大海原が広がっている。今回、デビューを果たした渡辺夏子のために、ご縁の方達が大勢励ましにきてくれた。スペシャルサンクスを!
小林身和子展
久々に小林身和子が銀座に再デビューした。04年の個展以降、結婚、出産、子育てと女の大事業に励み、五年間ほとんどまとまって絵筆を取る時間がなかったにもかかわらず、初志をまげずこのたび前線に復帰したことをまずは言祝ごう。
1972年東京生まれ1999年に女子美大日本画科を終了。在学中から創画展に入選するなど旺盛に作品発表を続け、2000年には村越由子・直野恵子と文月展を開催。当画廊とはこれが縁で02年と04年に個展の運びになった。
以後、今展までの道のりは並大抵のことではなかったと思う。しかし、小林はそれすらも力に変えてみずみずしい作品を仕上げてきた。岩絵具を重ね、何層にも盛り上げては金やすりで彫り、磨く。傍らで子供が遊んでいるというが、本人も夢中になって絵の層を掘り進んでいるに違いないと思わせる。
絵肌はまるで荒い麻布。布目のような方眼状の彫りを丹念に施した画面は複雑な色目をみせ、下の隠された層を想像させる。岩絵具の重厚なマチエールを彫って磨き、さらに重ねて彫るという気の遠くなるような作業を進めるに従って、次第に作品に密度がましもうこれ以上手が入らないところまでやりたいのだ、という。
50号の「刻む」と題された作品には、古代の壁画のような線が残る。堆積した時代やその風化まで思わせる絵肌だ。何度も繰り返された塗りと削りが見る人の心象と重なる瞬間を待つのだろう。この線と層の中に分け入って自由に想像の羽を広げればよい。 白い紙を前に時間を刻み、記憶を刻み、全てを刻み込んで描いた今展の作品は5年のブランクを感じさせないばかりでなく、更に進化していた。ストレートに飛び込んでくる印象と純化された色彩。思うように動けない日々さえ栄養にしておのれの世界を深めていったのであろう。
大河のゆるく深く流れる水のように描き続けていって欲しいと思う次第である。
西村亨人形展 スーパ—ソリッドドールズ III
馬上のプリンセスを引き連れて西村享の三回目の個展が始まった。西村のマニアックともいうべきアメリカ60年代への偏愛に応えて、常磐茂氏が以下のような文を寄せてくれた。
西村亨作品の幅ーーこんどはおなじみの美女たちが、さまざまな動物にまたがって登場するという。それをきいただけで、なんだかサーカスの開幕を待つときのような気分になり、カタルシスさえ覚えてしまう。アフリカ象やガラパゴスゾウガメ、カバもいるらしい。言わずと知れた、絶滅危機動物。と、そうなってくると、これは考えるところもあるかなと考えたりもする。こんなふうに、少したってから、もしやと、かすかだがメッセージのようなものを憶測させるところは、ちょうど落語の考え落ちというのに似ている。また上質な喜劇作品につきものの要素でもある。登場人物個々の性格までわかる描写力にも驚くが、自由に想像させる許容力にもハッとする。どちらも西村亨作品の持ち味だ。
2007年の悦子画廊デビューから、連続三年続けた個展。今展では上記の通り、動物に乗ったドールたちが勢揃いした。
西村亨は1961年生まれ鎌倉で育つ。1987年多摩美大油画専攻修了後は、日本デザインセンターでイラストレイターの仕事についた。その後CG全盛の世相に反逆するように、リアルな手仕事にのめりこむようになったという。
もともとミリタリープラモに夢中な子供時代を過ごし、成長期にはテレビでアメリカのホームドラマや、ヨーロッパの映画等から大きな影響を受けたというから、制作の種は足下にあったという訳だ。 映画「アメリカングラフティ」にとどめをさすアメリカの黄金時代をアイロニカルに、またコミカルにドールに託して表現している西村の仕事は今展でまたバージョンアップした。
アルミ線を軸にスタイロフォームで肉付け、粘土で細部を仕上げたあと丹念に着彩という過程を経て完成するこれらドールたちは、小さすぎず大きすぎず絶妙なサイズをキープしているが、西村は今展で巨大化をもくろんだ。ドールを下支えする駆体に動物を選んだのである。しかも馬や象、カバやらくだにガラパゴスゾウガメという大きなものばかり。
往年のハリウッド映画を彷彿させる美女たちは、それぞれの物語を背負い遠い彼方へ目線を投げる。一見ありそうで、絶対あり得ないシチュエィションを作り上げ、クスリとくすぐるとともに圧倒的な存在感を示すこれらの作品は西村の面目をまた一新させた。
さらに得意のワザをくり出し、メッサーシュミットやジープを精巧に作り上げ、紙と粘土で鉄のさびや匂いまで写し取るという離れ業をみせた。これらデティールへの異様なこだわりは、このドールたちの存在する時代へのリアリティとなって西村の仕事を支えている。
時代はザ・ロネッツの BE MY BABY が流れる底抜けに明るい時代。ドールたちはみな遠くを見つめ、未来にも幸せしかないと信じていた時代だ。わずか10年にも満たないようなピンポイントの時代に、西村の全感覚は集中する。日本に生まれて、ブラウン管やスクリーン、ラジオの音声からアメリカを吸収して育った世代ーいわば戦後に生まれたものたちが無作為に享受したアメリカ文化が、今こういう形で凝縮されて出て来たことが興味深い。しかも、諸手をあげて礼賛している訳ではなく全くの皮肉でもなく。ただここに時代を取り出してみせているだけなのだ。
西村は「クールに」作っている、という。いたずらに思い入れることなく無心に細部を追うという作業の果てにでてくるもの。幸せな未来を追うように強い視線を投げかけるドールたちは、その先に待ち受けている不毛な時代をしるよしもない。
神 彌佐子展
神彌佐子(じん みさこ)による当画廊三度目の個展が始まった。
父方は青森の旧家とか、「神」という名もこの地方由来ときく。アラフォー世代と思っていたが、そろそろ後半らしいのでアラフィフ?だいぶこちらに近づいてきた。 それはさて、武蔵野美大日本画科を卒業後は創画会 中心に大作を発表してきた神彌佐子。エネルギッシュな造形力とともに、たぐいまれな色彩感覚を駆使した作品に魅了されて、2000年に個展を依頼した。マグマとブラックホールが同居するようなドラマチックな展覧会だった。その後04年の個展などを経て今展に至る訳だが、その間文化庁の海外研修でフランスに渡りロマネスク絵画の研究をしてきたという。
また出身校の武蔵野美大の通信課程や共通絵画分野で講師をするなど、教師としてもキャリアを重ね、その過程で日本画の技法の研鑽を重ねてきた。
これらの経験が、今まで以上に彼女の才を花開かせた。内部に鬱屈していたエネルギーが出口を見つけて奔流となったような色彩の洪水は、見事に制御されつつ有機体のようにうねりをみせる。特筆すべきは、そのたらし込みの技法の見事さだろう。色を重ねる際に、厚塗りするのではなく、水をたっぷり使い水を走らせてニュアンスを重ねる。ショッキングピンクや緑、あらゆる際立つ色も水の力によって下品にならないのが不思議。
ゆるくうすく画面を覆う水は、時に留まり時に流れまさしく「方丈記」の如しーゼラチンの質感から画想を得たという「geratinous」はグミというお菓子の毒々しいまでの色と触感のイメージに、メキシコやパリで買い求めた紙や箔をコラージュ。増殖していく細胞のような構成の作品に仕上げた。
今展では画廊に一足踏み入れたとたん襲ってくる鮮やかな色の乱舞に驚かれつつ、歓声をあげた方が多かった。こんなにふんだんなピンクの渦は日本ではなかなかお目にかかれない。渋さ、重厚さばかりが芸術ではないだろう。鮮やかで有機的な色のダイナミズムが人の心に衝撃を与え、カオスに引きずり込む。日常から非日常への異化が始まる瞬間だ。その裂け目をつくるまでが画家の仕事で、それから作品に何を感じるかは見る人の仕事だ。
この混沌に人はそれぞれの記憶をたどる。キャンディやチョコレイトの包み紙の醸すキラキラした夢を思い起こす人もいれば、盛り場のネオンを思う人もいるだろう。千差万別の思いが錯綜する万華鏡と化して、しばしも留まることがない。神彌佐子がねらい、自らを託すのはそういう磁場なのだろう。
たらし込みの技法もまた、水に行方を託す。どこに流れるかわからない偶然の営為をも取り込んで、薄く濃く思いを重ねて行く。一枚の絵に向かい、その一回性の戦いに挑み続けているのが神彌佐子なのである。
その行為は時に痛々しくもあったが、10年の間に少しずつ殻が剥がれ今展ではそれを謳歌していた。真剣勝負の楽しさに満ちていた、といってもいいくらいだ。イチゴやパパイヤなど果物をプレスし、原形がわからなくなくなったものを再構築していくという作画で描いた小品たちも楽しいインスピレーションに満ちたものだった。
単色でみれば毒々しい色も神彌佐子の魔法にかかれば、なんと魅惑に満ちた色の連なりになるのだろう。天性の色感にいっそう磨きをかけ、透明感を増した作品たちはそれぞれに響き合って光を放ち画廊中に充満する。
「わたしにとって制作はダイレクトな身体表現である」という神彌佐子の真骨頂は、見た人の脳髄に直接響くストレートさがあることだろう。理屈抜きに反応する感情、あるいは理不尽な情動を人は制御していきている。その間隙を縫って神彌佐子の作品は飛び込んでくるのだ。判断以前の直感を呼び覚ますー嗅覚や聴覚に近い反応を視覚であらわす、という仕事なのだと思う。
このアマノウズメノミコト的乱舞に堅い扉も「ひらけゴマ」。姓が「神」名が「ミサ」というのもうなずける次第というもの。ご見物衆は如何ご覧いただいたであろうか。画像はご来廊の方々の一コマご紹介まで。
清水研二朗展
清水研二朗の銀座デビュー展が始まった。
清水は1976年京都生まれ。約一年の渡仏を経て、2001年に多摩美大日本画科を卒業している。在学中の2000年に都下鷹の台で初個展、2002年に神田で個展の他、グループ展や壁画制作など旺盛な活動をしていたが、その後仕事が多忙になってきたため一時発表を控えざるを得ない状況が続いていたという。 今展は実に七年ぶりの発表。また、描くテーマも大きく変貌を遂げての再スタートとなった。卒業まもなくの個展では人物の形を通して造形表現をしていたが、このところコツコツ一人で描いていたのは、蛙というあらたなモチーフ。もちろん蛙そのものというより、その形を借りて回遊式庭園や山水が描かれているわけだが、この大きな転回のきっかけとなったのは、沈黙の間に培った古典の勉強と、なりわいとしてきた造園の世界との出会いだ。
在学中にフランスに渡り、ヨーロッパ各地の美術を感得してきた清水が向かった先が現代美術っではなく日本の古典だったところがまず面白い。肌にあうか合わないかは実際に肌で感じてみるしかないが、結局のところ蕪村にいきついたのだという。水が添うように自分にとってすんなり落ち着く場所、またそれが一番エキサイティングなところでもある。自由自在な筆さばきの蕪村画は爛熟した江戸期の精髄そのものー古典の画集をめくる間にその芳醇さに気がついた清水の画想も自然その方向に傾いていく。
またそれを後押ししてくれたのが、仕事としている造園業の親方の姿勢だった。作庭といえば誰もが土の上の仕事と思うが、実は地面の下の仕事の方が大事だとその理を教えられたのだという。上が生気あるれているためには下の環境を整えるー逆に下が整っていれば上は自然に伸びる、という摂理は造園のみならず全てにあてはまることである。
これらの事を徹底的に体で覚えた清水は頭だけで考えることを止め、画想がリアリティをもつまで練りに練った、一見荒唐無稽に見える蛙式庭園「かえるもの」は、親方も驚く程よくできた庭園設計図だったことが一つの成果だろう。また私の好みでいえば、さらにそこから色んな計らいを取り除いて、空間が美しい「雫」が今展の収穫だった。綿布に薄く土を塗り、さらにそれを洗い、自然な古色を帯びた空間はどんな装飾より美しいと思わせてありあまる。しかも緑が清新で若々しいのが嬉しいではないか。
蛙の絵を描く前、鎌倉の自宅門扉にモリアオガエルがちょこんと乗っていたのだという。普通深山に生息する蛙であるが、この美しい緑を描かせるために姿をみせたのではないか、と因縁めかしたくなるエピソードである。
七年ぶりの個展を支えてくれた夫人の木下めいこ画伯やご家族、また親方ファミリー、ご友人などがご来郎下さった。これを糧にさらなる飛躍を願ってやまない。
尚、画像三枚目は19日に都心各地で行われたtokyo milky wayのイベントで、画廊の電気を消してろうそくで絵をみる光景ー怪しい一コマではありません(念のため)
小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.2
小松謙一と藤森京子による日本画とガラスのコラボレーション展が始まった。このユニットで制作する『アオゾラとガラス』たちが今年も画廊にやって来てくれた。サーカスではないが旅する一座のように、決まった季節にやってきて、ポケットから「はいっ!」とアオゾラの詰まったガラス玉を取り出してみせてくれる‥。それを覗き込むとかれらの旅した一年の記憶が幾重にも堆積してきれいな層をなし、光に包まれて表れてくる、といった塩梅だ。
1959年生まれの日本画家・小松謙一は水の流れや雲の動きなど、一時も同じ表情を留めないものをモチーフとして、微妙な心の揺れなどを託して描いて来た。また余白を意識した空間表現でどこまで万象の存在の大きさに迫れるか、意欲的に大作に挑んでいることで知られている。
一方、藤森京子は1977年生まれ、小松と同窓の多摩美で工芸デザインを専攻し、卒業後は繊細なカットを特徴とするガラス作家として道を歩み出している。
常に新しい表現はないかと制作を進める小松が絵を立たせる事は出来ないか、と考えたのがそもそもの発端らしい。平面の限界を突き破りたいと絵の裏側を見せる工夫を藤森の仕事に託したという。和紙に重ねた絵具の層がガラスに挟まれて光を透過させる。岩の粒子の窓、箔の層、何層にも重ねられたガラスが鉄の台の上に直立する。 あるいは寄木細工のようにカットされては組み立てられた色の砕片による家。そして何よりもの収穫は、絵具が乾いては消えてしまう濡れた色をガラスに封じ込める事に成功したことだろう。
平面という制限を乗り越え、タブーをタブーと思わない果敢な挑戦はガラスという異素材と出会うことで、不可能と思われていたことを可能にした。のみならず、二人のコンビネーションはそれぞれの世界から違う魅力を引き出して、さらに別の世界へと向かおうとしている。
孤立した制作からユニットとして試行をはじめた二人の今回の仕事では、今まで材料を投げかけていた小松が初めて受け取る仕事をした。個々の仕事から派生して自分の仕事以上のものを相手から受けるーあるいは自分が与えるというのはお互いの信頼と尊敬がなければ成り立たない。その希有な関係があればこそのコラボレーションといえよう。
目指すのはアオゾラ。水や空気が単体では透明なように、日々の営みを一枚一枚ベールにして重ね、奥行きのあるアオにしていく。一個の作品を生み出すための葛藤や錯誤、発見や喜びを幾重にも重ねたさきに深みのあるアオゾラが生まれる。ガラスに重ねられる色彩もまた、そのアオゾラに至るための道しるべなのだろう。こうして気宇壮大な世界観を持つ小松謙一の中に潜む繊細なロマンティズムと、針の先ほどの感覚に耳を澄ます藤森京子がもつ不屈の合理性は一つの作品のなかにらせん状に絡まり、アオゾラの結晶として銀化していくのである。
そして今、ガラスを包んでいた風呂敷をひろげ、一つ一つアオゾラを取り出しては画廊に窓を穿ってくれた。日本画とガラスという異素材をさりげなくマリアージュさせてくれる額の役割にはさび色も美しい鉄。小松にアトリエを提供し、懇切に溶接やら腐食を教えて下さった鍛金家のご夫妻・市岡さんと留守さんもご来廊、出来映えを見て下さった。また、空手の上達のため見事ダイエットに成功してさらに美女度をあげたちさと嬢の鎖骨あたりには、アオゾラガラスペンダントがキラリ。わたしも小さな手乗りアオゾラが欲しくなった。みなさまはいかが?
小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.4
小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.3
小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラス
永江俊昭陶芸展
沖縄八重山、その中でも最も南に位置する波照間島に産する土を使い、様々な技法を駆使してその魅力を最大に引き出そうと制作する永江俊昭。沖縄に魅せられ、歌の師匠の元に通いつめるうち、島で昔制作されたという陶の話を伝聞し、窯跡を探し当てることから彼の「波照間焼」は始まった。その経緯については彼が用意したステイツメントに詳しいから下に記す。
古来「神の島」ともいわれ、神行事、古謡が多く残る沖縄においても有数な歴史を誇る島であります。
その波照間島でも昔は、家屋用に琉球赤瓦を島内で焼き、島内に窯を築き、瓦の他にも甕などを焼成していた様子です。しかしその窯も今は無くなり、瓦はじめ陶器を製作することもなくなりました。
かつて八重山では、有名な「新城(パナリ)焼」というものが新城島で焼かれていましたが、波照間島においてはあえて「波照間焼」というものは存在していなかったようで、この度、波照間の土を使い、波照間の素朴な雰囲気を残しながら懐石食器、茶道具、壷類、雑器に至るまでを製作すべく「波照間焼」を興しました。
目の細かい、焼き締まりのいい素晴らしい土質で、焼き上がると赤色に発色します。ただ、耐火温度が低く薄造りには不向きですが、洗練された中にも野趣に富み、波照間島独自の空気を映す作品作りを心がけております。
また、波照間の海には、ダイバー達の間で時に「波照間ブルー」と呼ばれ、ダイバーたちが憧れる美しい海があります。その海の深い青色を表現すべく「波照間青釉」と称した青い釉薬の作品をはじめ、焼き〆陶、刷毛目粉引き等の技法を用い作品作りをしております。 永江俊昭
1984年芦屋市滴翠美術館陶芸研究所から始まった永江俊昭の陶歴は李朝陶磁への傾倒から、中国古陶磁、古唐津、京焼きへと進み、更に刷毛目、粉引き、三島、織部とその枠を広げて来たわけだが、波照間の土を発見することによって新たな境地に導かれたといえよう。
古陶の完成された世界から、自らが興す未知数の世界へ。この大きな転換を問うべく今展の次第となった。おおらかで神話的な島の風光に魅せられる人は多いが、すでに捨てられて顧みられなくなった窯あとを探し、土の在処を問うて歩いた熱意と「波照間焼」という名で自らが可能性を切り開くという自負によって、永江俊昭は世に「波照間」を知らしめ、さらに島との密接な関係性を築くこととなったのである。
その恩人である八重山民謡の師・後冨底周二先生のお兄様ご夫妻と今展の総合プロデュースを引き受けてバックアップして下さった小林社長、そしてそのファミリーの皆様が初日に駆けつけて下さった。心から感謝を申し上げたい。
平野俊一展 in the garden
満開の八重桜のもと、平野俊一の花シリーズin the gardenが始まった。足下に広がる野の花を描くようになってからかれこれ4年はたつだろうか。今展、紛れもなく「Hiranoの花」といえる世界になっていることにあらためて気付いた。
2002年、当画廊での初個展。以後ほぼ毎年その歩みに同道してきた。平行して開催するグループLABO展では、毎年果敢に違う画風に挑んできた平野だが、「花」シリーズは意識して歩をとどめ、集中して描いて来た。昨年あたりから焦点をぼかした印象の花を「ゆらゆら」と描きはじめる。
この作風を「目の括約筋が頑張らなくてもいい」と評した人がいたが、まさしく滲んでいく色がやさしく目にひろがる。
仕事でミリ単位の細かい作業を重ねる平野が、ある時目を上げると別の景色が広がっていたのだという。老眼というお年頃になっていたのだ。その目に映る花々の美しさ。細部の見えない、純然とした色の塊として「花」を認識した時が、平野の「花」とのファーストコンタクトだった。
以前から、雨や雲、空といった気象の変化ーあえていえば「時間」を描いてきた平野。刻々と変化する気象を肌で感じ、その行方に目をこらすことで心の揺れと共振させてきた。
一秒とて同じ時間はない、が絵を描くという行為はその流れ行く時を切り取り「永遠」に孵化させる力をもつもの。
変わっていきたい平野が「花」のもとにしばし留まろうと思ったのは、美しい色の塊として見た花に「一秒」と「永遠」と同時に感じたからではないだろうか。
風にゆらぎ、刻々と開花し散るという営為を一枚の絵に留める、というのは至難なことではあるが、お年頃の目は細かいところがよく見えないため、大局がつかめるという利点がある。
今展での平野の筆は目の代わりになって、一枚の絵の中に複数の見え方を同居させた。よく見えたり見えなかったり、近づいたり遠ざかったりする視点が混在する不思議な画面だ。「花」そのものというより、「花のある空間と時間」ということなのだろう。-in the garden-とはいいえて妙である。
またしても不肖柴田は、この秘密の花園に踏み込んだあげく迷って出られなくなってしまった。時間と空間が奇妙に入り組んだ「花」たちの間を彷徨う黄金週間となりそうだ。どうか探さないでね。
中川雅登展
中川雅登日本画展が今日から。
1968年 愛知県豊橋に生まれ 1987年愛知県立芸大美術学部日本画科に入学し、92年に同学部中退。その後も愛知芸大模写「法隆寺金堂飛天」「西大寺十二天像」に従事する。2004年から名古屋で個展やグループ展で作品を発表しはじめ、東京では今展が栄えあるデビュー戦に。
画像でご覧の通り繊細極まりない画風。300鉢もの草花を自ら育ててスケッチしたものを下敷きに16点を描いた。今回はご近所の西邑画廊さんでこのスケッチも同時に発表、二会場で本画とスケッチ双方の魅力を披露した。
ご本人のもともとの気質と模写で鍛えた技術があいまって、今時珍しいような正統的花卉図ではあるが、モチーフとしているクリスマスローズはようやく近年日本でも知られてきたキンポウゲ科の花。そのモダンな容姿が古典的な描法で描かれているところが今展の見どころであろう。
丹念に平刷毛で塗られた空間にデリケートに置かれた岩絵具。息をつめて筆を置いている様子が偲ばれる。このような仕事に大作は過酷だ。50号の花菖蒲もどのくらいの期間を費やしたのか、想像を絶する。だが伴清一郎氏の作品を見て小品でも密度があれば大きさは関係ない、と感得。以来、小品にも心血を注ぐようになったという。
その甲斐あってどの作品にも匂うような品格がある。この品にさらに力強さが加われば、いずれ花卉図の世界の継承者のして世にしられるのは間違いない。一枚の葉、一枚の花弁のなかの神秘に分け入って、その美を余すところなく表現することに夢中で、俗から背を向けているように見える氏ではあるが年齢わずか40余歳。まだ仙人になるには若いお年頃。豪腕で描く細微な世界がこれからどう進化していくか、楽しみにしていようと思う。
竹内淳子展
「チベット絵日記」<> 竹内淳子の二年ぶり四度目の個展が今日から。
九州は小倉生まれの玄海育ち、由緒ある名刹の末娘が京都のある宗門の大学の文学部に入学したところからこの物語は始まる。
正しいお嬢様の進む道まっしぐらに国文を勉強していた彼女の目に飛び込んで来たのが、京都に数多い美術館の絵だった。本を繙くより、絵を見ている時間の方が多くなって来た頃、日本画を描いてみたいと専門学校に飛び込んだのだという。京都の凄いところはそこに日展の村居正之先生や畠中光享先生がいたことだ。結局、卒業の頃に先生方がお父様の方丈を説得して下さり、京都造形大の前身、京都芸術短大に入学、上記の先生や竹内浩一先生の指導を受けることと相成った。
一見、国文に日本画は正しいお嬢様の道のように見えるが(柴田もほとんど同じコース)、実はこれがけもの道の始まり。1988年二十代も後半にさしかかっていよいよ卒業するという頃、たまたま行った上海で異様なオーラを発散しているチベット人を見かけて衝撃を受ける。これもお嬢様の常ながら、欲しいものにはまっしぐらーこの衝撃の訳を究明すべくただちにチベットに向かう。以後20年、のべ一年余をかけてチベット各地の道なき道を踏破する。
言葉もわからず一人の手探りで始まったチベット彷徨も、今では「地球の歩き方」に紹介されるようなチベット通になった。道ばたに座り込んで描いたチベットの子供達や,老人のスケッチも数えきれない。高山病でふらふらになりながら休憩の時にはロバを描く。体全体でチベットを感じて来た歳月だった。
故郷や京都で描きためた作品を発表し始めた頃、出会った骨董店「昔人形・青山」のK一さんに一目惚れ。かなりの年の差を強引に押し切りめでたく結婚、いまや愛猫二代目クッキーをしたがえ押しも押されぬ「時代屋の女房」だ。
ところが、東京進出を企て畠中先生から紹介された先が、この柴田悦子画廊。お嬢様のうえをいくお嬢様の画廊だったものだから、けもの道にさらに拍車がかかった。真綿でくるんで大事にされた初回のあと、同じつもりで来たらいきなり画廊主はニューヨークへ。後を任された小黒氏妻・早苗ちゃんとともに泣く泣くお留守番の悲哀を味わうことに。獅子は我が子を谷底へ突き落とす作戦は効を奏し、画廊主が帰国する頃には二人手を取り合って「柴田さんがいなくても平気!」と宣ったもの。
それはさて、そんなこんなで京都での個展をなかに挟むので隔年になる個展だから都合八年になる付き合いだが、毎回極彩色の残像を置き土産としてくれる。他の誰でもない竹内淳子の色彩の残像は強烈だ。あか抜けない、といってもいいような土臭さを内包してどうだ!とばかりに光り輝く。晦渋とか枯淡という言葉の対極にこの徹底した肯定の世界はある。生き物としてのパワー、、この異様にも見える強さは疑うことを知らない、その必要のない世界が持つものだ。
神々の山、神々の民ーー上海でそれらに引かれるように出会ってしまった竹内淳子だが、その物語の序章に最初のエンカウンターが隠されている。それは先代ご住職の蔵書が納められた書庫で遊んでいた彼女が見つけた「大蔵経」。その背表紙の字をみるとワクワクしたという。もちろん中身を読んだ訳ではないが、大切な事が書かれたものという印象を深くもって、以降「蔵」の字をみると反応したらしい。チベットは漢字で書くと「西蔵」。やはり縁としかいいようのないものがここにある。
今展に先だって、ご実家の寺の襖絵を描く機会を得た画伯は、長い旅を経て「蔵」の出発点に戻り「迦陵頻伽かりょうびんが」という仏の声を形容するともいわれる伝説上の鳥を描いた。絢爛豪華な作品を襖にして納めてみると、寺の内陣の陰影に富んだ光線によって、刻々と金箔のニュアンスが変わりさらに美しく荘厳されるのを目の当たりにしたという。
作品が画家の手を離れて、光や時間によって様相を変えていくーこのダイナミズムは作家のエゴをはるかにこえる。あとは祈るのみだ。
今展ではその仕事をふまえ、「チベット絵日記」と題して大作三点を含む十三点をご紹介。とくに奉納作品と同サイズの大きさに描いた「西のロバ」が収穫だった。ロバの巧まざる存在感と過不足ない装飾が一つの境地を示していたと思う。いつまでも見飽きない、もっと見ていたいと思わせる「魅力」に満ちた作品だ。誤解を恐れずにいえば、なんでもないもの。それが他の要素を呼び寄せるー内陣の光のように。
さて、そろそろこのロバの休憩時間も終わったようだ。青山の旦那が手早く天幕をたたんでいる。竹内淳子のキャラバンは次の露営地を目指して早くも出発進行!私も「竹内淳子物語・我田引水ダイジェスト版の巻」を巻き了えるとするか。
佛淵静子日本画展
昨年に引き続き、二回目となる佛淵静子の個展が始まった。
「ほとけぶち」という珍しい姓は鹿児島出身の父方のものとのことだが、本人は1974年に東京で生まれた。’98年に多摩美術大学美術学部日本画専攻卒業、’00年に同大学院の修士課程絵画専攻を修了すると翌’01年には初個展。以後、個展グループ展他公募展にも積極的に出品し、旺盛に制作をしている。この一月には日動画廊・昭和会展招待になるなど、ジャンルを超えた活躍が目覚ましい。
当画廊とのご縁は’07年の日本画四人展「plus#1」展から。翌’08年の個展では黒のドレスの四連作で月の満ち欠けを表現した作品が記憶に新しい。
今年はどんな挑戦をしたか?
まずDMの作品から驚かされた。ナースが奇妙なポーズをとっている。しかも紙の地にはほとんど彩色が施されず、わずかな描写でなりたっている作品だ。今展のナース連作6点のなかで、一番省略がきいて線が目立つ。しかも15号というサイズに全身を入れて無理のない作品に仕上がった。鉄線描というか、抑制の効いた的確な線にわずかに加えられた衣装の白と手先の朱が、イラストでもなく漫画でもない日本画独特の存在感を現して際立つ。
先に驚いたと書いたが、ナースの衣装や奇抜なポーズもさることながら、昨年の墨のたらし込みによる黒のドレスシリーズの時には物足りなく感じた「空間」が出来ていたことへの驚きが一番強かった。何も描いていない生の紙に奥行きと広がりがあるのである。いかに描くべき対象と真摯に向き合ったかがわかるというもの。
昨年入院した彼女はテキパキ働く看護士の動きの美しさに改めて気付かされるという経験をした。「制服」というものが持つ機能は、それを身につける人間の個性を抑制するが、抑制することによって際立つのが個性。今回はその象徴としての「ナース服」とモダンダンサーの奔放でキュートな動きを組み合わせることで、そこにわずかに生まれる違和感という衝撃を絵にしたのだ。
「ナース服」という、ある種エロティックな幻想を呼びやすいものに敢えて挑戦した彼女の描きたかったのは、システィマテックで清潔なエッセンス。一本の線が緩んでいたら、この清潔さは容易くエロティックなほうに傾くだろう。その危うい橋を佛淵は真剣に渡り切った。
また前回の黒のドレスに対しての白ということでいうと、和紙の白に白を描くのは更に難しい挑戦だったはず。描写をどこまでするか、削る作業は自分の技量との勝負になる。6作並べてみるとその葛藤の過程がつぶさに見えるようだ。作品として成り立つぎりぎりを攻める、、。迷いも魅力だが、引ける線は一本。そのスリリングな緊張感が生み出した今回の「空間」だったように思える。
かくも魅力的な「空間」と「線」だが、さらに負荷をかけて描かない超美技を身につけてほしい。世の中に細密緻密の名人は多いが、その密度が一本の線に集約されていたら、どんな凄いことか。
私の要らぬ夢想は別として、今展会期中に美術倶楽部で開催された「アートフェア」中に出品されていた安田靫彦画伯の白描画をみて、佛淵の仕事が先人の掘り起こした軌跡に繋がる可能性をみる思いがしたことを記しておこう。
もちろん自身の嗅覚を信じて行くことに尽きるが、猛虎の内面を合わせ持ちながら抑制の美学を良しとする彼女が次に向かう先がどこなのか、楽しみに待たれることだ。 昨年に引き続き、二回目となる佛淵静子の個展が始まった。
「ほとけぶち」という珍しい姓は鹿児島出身の父方のものとのことだが、本人は1974年に東京で生まれた。’98年に多摩美術大学美術学部日本画専攻卒業、’00年に同大学院の修士課程絵画専攻を修了すると翌’01年には初個展。以後、個展グループ展他公募展にも積極的に出品し、旺盛に制作をしている。この一月には日動画廊・昭和会展招待になるなど、ジャンルを超えた活躍が目覚ましい。
当画廊とのご縁は’07年の日本画四人展「plus#1」展から。翌’08年の個展では黒のドレスの四連作で月の満ち欠けを表現した作品が記憶に新しい。
今年はどんな挑戦をしたか?
まずDMの作品から驚かされた。ナースが奇妙なポーズをとっている。しかも紙の地にはほとんど彩色が施されず、わずかな描写でなりたっている作品だ。今展のナース連作6点のなかで、一番省略がきいて線が目立つ。しかも15号というサイズに全身を入れて無理のない作品に仕上がった。鉄線描というか、抑制の効いた的確な線にわずかに加えられた衣装の白と手先の朱が、イラストでもなく漫画でもない日本画独特の存在感を現して際立つ。
先に驚いたと書いたが、ナースの衣装や奇抜なポーズもさることながら、昨年の墨のたらし込みによる黒のドレスシリーズの時には物足りなく感じた「空間」が出来ていたことへの驚きが一番強かった。何も描いていない生の紙に奥行きと広がりがあるのである。いかに描くべき対象と真摯に向き合ったかがわかるというもの。
昨年入院した彼女はテキパキ働く看護士の動きの美しさに改めて気付かされるという経験をした。「制服」というものが持つ機能は、それを身につける人間の個性を抑制するが、抑制することによって際立つのが個性。今回はその象徴としての「ナース服」とモダンダンサーの奔放でキュートな動きを組み合わせることで、そこにわずかに生まれる違和感という衝撃を絵にしたのだ。
「ナース服」という、ある種エロティックな幻想を呼びやすいものに敢えて挑戦した彼女の描きたかったのは、システィマテックで清潔なエッセンス。一本の線が緩んでいたら、この清潔さは容易くエロティックなほうに傾くだろう。その危うい橋を佛淵は真剣に渡り切った。
また前回の黒のドレスに対しての白ということでいうと、和紙の白に白を描くのは更に難しい挑戦だったはず。描写をどこまでするか、削る作業は自分の技量との勝負になる。6作並べてみるとその葛藤の過程がつぶさに見えるようだ。作品として成り立つぎりぎりを攻める、、。迷いも魅力だが、引ける線は一本。そのスリリングな緊張感が生み出した今回の「空間」だったように思える。
かくも魅力的な「空間」と「線」だが、さらに負荷をかけて描かない超美技を身につけてほしい。世の中に細密緻密の名人は多いが、その密度が一本の線に集約されていたら、どんな凄いことか。
私の要らぬ夢想は別として、今展会期中に美術倶楽部で開催された「アートフェア」中に出品されていた安田靫彦画伯の白描画をみて、佛淵の仕事が先人の掘り起こした軌跡に繋がる可能性をみる思いがしたことを記しておこう。
もちろん自身の嗅覚を信じて行くことに尽きるが、猛虎の内面を合わせ持ちながら抑制の美学を良しとする彼女が次に向かう先がどこなのか、楽しみに待たれることだ。
板東里佳展ーShadow of Color
四日前まで摺っていたというほかほかの新作を抱えて二年ぶりに板東里佳が帰ってきた。版画家・板東里佳とのご縁は2000年の個展-Streams of New York-に遡る。以来、二年に一度のペースで発表を続け今展で五回、早いもので十年に及ぶ道中となった。
板東里佳は1961年東京に生まれ、1984年に渡米するとニューヨーク・アカデミー・オブ・アートで1990年まで彫刻を学び、その後2000年までアート・ステューデント・リーグ・オブ・ニューヨークでリトグラフのコースをとっている。
在学中の1999年にJames R.and Ann S.Marsh・メモリアル・バーチェイス・プライズ ハンタードン美術館で賞を受けたのをはじめ、意欲的にコンクールやグループ展に出品して受賞。2000年からはいよいよ日本とニューヨークで個展を開催し始める。
それ以降の目覚ましい精進ぶりはあえてここに書くまでもないが、作品世界の深まりとそれを支える高い技術力として結実し、緊密で浄化された世界へと私たちを誘う道標となったのである。
私が見た作品の、最初はメイソン・ジャーシリーズだった。彼女がいつもいる台所からみた窓際の光景。そこにさりげなく置かれた保存用のレトロな瓶。その瓶に映り込むブルックリンの光景は、透明な光に満たされた美しい断片だった。清潔で、だからこそ少し孤独な陰影を感じたことも。
次に見せてくれたのは、その窓を開けて下を見下ろしている構図だった。雪解けの道に車が付けた轍。その無作為な抽象の面白さを丹念に構成した作品や、白をいかに美しく見せるかに心を砕いた雪景色などの一連の風景シリーズである。
また次には外に飛び出し満開の桜を描いた。桜のあでやかなピンクの隙間から無窮の空。これ以上ないというきりりと粋な桜花ー取材したブルックリンと北海道の桜はともに大輪で見事な姿だったという。
友人の句に「雲を透き 花を透かして 降るひかり」というのがあるが、次に里佳さんが向かった先は光に一番近い雲。雲のドラマもまた見飽きないものの一つだが、「天使の階段」と英語で言われるところの、雲間の光に挑戦。雲を透かして光が織り成す一瞬のショーを白と黒で見事に表現した。
前回はその光が地上に届いて地面に陰影を与える「木漏れ日」がテーマ。風のそよぎとともに一時も同じ姿を留めない揺れ動く形象を、ごく薄の手漉き和紙「阿波紙」に託して刷った。紙を洗濯ピンでつなぎ壁に添わせた展示とともに印象深い。
こうした軌跡を経て、今回のテーマである「Shadow of Color」に至るわけだが、「光」を描くために木の「影」を丹念に描くという発想は、どこか東洋画の思想を思わせる。地面に揺れる木漏れ日から木の幹へ焦点は変わり、光が作ったシルエットとして樹々が表す情景をこれ以上ない位ほど緻密にとらえている。
このように繊細にものごとを感じる人の常として、画面の隅々まで神経が行き届くよう仕上げるものだが、今展で私が感じた大きな発見は「余白」である。リトグラフの黒を白の幅をメゾチントの幅まで広げたいと技術に磨きをかけて来た板東里佳の仕事は、黒のニュアンスを広げるとともに、「何もない」とおもわせる「余白」の白にたどり着いた。
手を抜いている訳ではなく、計算されつくした白の空間。白が空間として成立するためには、黒がよほど描けてなくてはならない。今展の制作を通して、そのためのあらゆる努力をした姿が偲ばれる。
“Simple Gift”Pin Oak と名付けられた4連作ではこの「余白」が見事に生かされ、光が自在に樹々と戯れ、様々なムーブメントを作り出しているさまが見事に描かれている。鉛筆の風合いが出るように、インクの調整に気を配り、色の深度まで計算して版まで変え、しかもその努力の跡がみじんも作品にとどまっていない。これは凄いことだ。
最初、なにげなく見えたものが時を追う毎に深みを増して、色んな姿を見せはじめるー一週間、この作品たちとともに過ごした私の実感である。これら今展の作品たちは「生き物」のように見る人の心を巻き込んで動き出すだろう。傑出した作品と思う所以である。
松崎和実展ー箔画Ⅱー
松崎和実の箔画による展覧会が始まった。松崎は1969年宮崎県生まれ。96年に上京し、墨を使った画家集団ISAM(International Sumi Art Movement)に参加、墨を使った実験的な作品に挑んでいく。数々のグループ展や国際展を経て、2004年に初個展。その後、薄美濃紙の上の箔に描き、切り抜いたものをアクリルの板に挟んで額装するという離れ業を編み出し「魚類」をテーマにユニークな制作を続けている。
二人展も含めると二年ぶり三回目になる今展でもその驚くべき超絶のワザで圧倒し、彼の描く魚たちのリアリティはご見物衆の目から鱗を取り払ってうならせている。
もともと墨のつけたてを修業した腕があるうえに、魚たちに対する突き詰め方が尋常ではない。いかに生き生きと自分が感じた魚を描くか、を追求したあげく描いた魚を紙から切り離すという、普通思いつかないような発想を得たという。浮かび上がらせて光を当てると額の底に魚影ができるーこの影が絵に描いた魚にさらなるリアリティを与え、美しさを添える。
この技法に「箔画」と名付け、二年の歳月を費やした一対の大作が今展の収穫。春夏と秋冬の旬の魚たちを螺旋状に描いた「魚の柱」はその描写の細密さと形状のシュールさが相まって見事な海の物語となっている。
もともと江戸時代のある藩の魚類図譜から啓蒙されたという魚作品だが、すでに図鑑のレベルをはるかに超え魚類の神話とも言うべき世界を紡ぎ出しつつあるように思う。
この没頭が生み出す狂気のような力はタブーを恐れない。江戸期の若冲にしても狩野派全盛の時分にあっては異端の謗りを受けていたというではないか。誰も見た事がない世界を描きたいという野望は自分自身さえそれがどこから来ているのかわからないものだろう。
松崎の目指している先がどこであれ、自分が静かに熱狂しまた回りもその熱を共有できるような世界であることは間違いない。そのメッセージを発信するのに絵筆という得物を見つけ、自在に発想していく勇気と追い求める根気をもつ彼が、私たちをどこまで連れていつてくれるかーーこの「海の神話」に魅せられた私の期待はいよいよ増すばかりである。
Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20