 お嬢さんの芸大入学式帰りの安住画伯がご来廊。すてきな着物姿の帯は、去年の茅ヶ崎茶会の時に徹夜で描いた桜満開のもの。一年の早さに思いを巡らしていたら、茶会の発起人、春彦さんが登場。
お嬢さんの芸大入学式帰りの安住画伯がご来廊。すてきな着物姿の帯は、去年の茅ヶ崎茶会の時に徹夜で描いた桜満開のもの。一年の早さに思いを巡らしていたら、茶会の発起人、春彦さんが登場。
きものや帯に自分の絵柄が描けたらいいだろうなぁ、などと考えている画伯たちを集めて、自作着物による茶会が開けたらさぞやすんばらすぃ~事に。
人物画で知られる日展の福田千恵先生は、何かにつけてアズピ画伯を気にかけて下さるお方。今日も励ましの言葉をいただく。
夜は作品撮影のある画伯を画廊に残し、悦子は俳句友達・さくらさん、マダム井澤、ハイジさんたちと近松芝居を見に。夜遊びは女友達に限る?
先生大集合!
 今、やる気全開のあずぴ画伯のために次々と先生方がご登場、ありがたいご教授を。
今、やる気全開のあずぴ画伯のために次々と先生方がご登場、ありがたいご教授を。
先日の米谷先生に続き、多摩美教授の中野嘉之画伯のご講評。今回先生の書かれた技法書を読み、改めて師の偉大さに気付いたアズピ画伯だが、朝5時から膠を煮る中野先生のバイタリティも見習いたいもの、と悦子も。
日展の雄、土屋禮一画伯も絵を見ていて下さる御一人。両雄に挟まれたあずぴ画伯はほんまに幸せもんや、としみじみ感じる。
また、府中美術館の館長にして多摩美教授の本江氏も激励を。精神科
のドクター山下先生はニュージーランドからのお客人を伴って。
画家仲間では、お元気印・北村さゆり画伯と、個展が終わったばかりの依田万実画伯が久々のお目見え。一年先輩になる依田画伯、卒業以来の再会になる中野先生に少し緊張気味。私たちを教えていた頃の先生ってまだ30才そこそこだったんだよね、と感慨を深くする。
まだまだ、自分を大人と思えない私たちって、何時大人になるんだろう…?
ドクターみっちゃんのお留守番
 せっかくのお休み、なのに悦子画廊のお留守番役のドクターみっちゃん。悦子はちょいと抜けて半沢先生の所属する千代田フィルのコンサート。お仲人さんの藤井先生のご一家がちょうどいいタイミングでいらしてよかった事。
せっかくのお休み、なのに悦子画廊のお留守番役のドクターみっちゃん。悦子はちょいと抜けて半沢先生の所属する千代田フィルのコンサート。お仲人さんの藤井先生のご一家がちょうどいいタイミングでいらしてよかった事。
みっちゃん中学同級の高取さんご一家もにぎやかにご来廊。
日曜なのに夕方からぞくぞくご見物衆がお見えの今日、恩師よねちゃんこと米谷清和先生と加藤晋ちゃん画伯など多摩美ーズの面々。
また、ギャラリー和田で個展中の遊馬画伯もご来廊。この方は悦子画廊ご用達いっちゃんの愛知芸大友達の画家さん。折しもそこにいっちゃんがゲットしたガールフレンド瑞穂ちゃんが登場して、またしてもシンクロしてしまう画廊空間。一週間前、大江戸助六太鼓を聞きにいったのはこの瑞穂の晴れ舞台だったのだ。忙しいこの二人が画廊にこれるのは実に稀なのに、会っちゃうんだなぁ。この日は瑞穂ちゃんが舞台をつとめていた鼓をもっていらしたので思いがけずポーンの音を堪能させてもらった。
林田画廊の元看板娘・米田さんも超お若い格好で、悦子とポーズ。もちろん、諏訪の御柱帰りの武大人ものりのりで「山の神様お願いだぁ!」
織田有紀子展初日ー有紀子日本に目覚める!
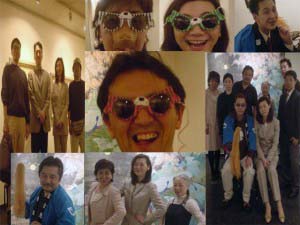 染井が散って八重が花満開のさくら通り。今が女盛りのアズピ織田有紀子画伯の個展にふさわしい幕開けとなった。
染井が散って八重が花満開のさくら通り。今が女盛りのアズピ織田有紀子画伯の個展にふさわしい幕開けとなった。
毎年心境いちじるしいあずぴ画伯の今年のテーマは「たゆたふ」。去年、国文学々界のマドンナ島内裕子先生に「臈長けた」とお褒めに預りながら、「それって老人力のようなもの?」とかましまくった画伯。
今年はいくらか御勉強なさったらしく、めきめき日本の空間美にめざめ藤色の背景に蓮のたゆたふ景に挑戦、まさしく臈長けた世界を展開させた。
あでやかでありながら余白にやや野生味を残したところが今年の手柄か。沖縄取材で写生したカメレオンの「M氏」も見事にものにしてみせた。
額装でお世話になった数寄和の岸田さんに技法上のアドバイスを受け満身創痍となりながら日本画の空間に挑んだ画伯、全身にやる気を漲らせながら諏訪から登場。前日の搬入は夜の9時半から。子犬君運送のみそそ画伯旦那たっちゃんが「合点だぁ!」と超短時間で仕込んでくれた展示、見事にはんなりたゆたふ空間に。
初日一番は御大・林信夫画伯 。数寄和の岸田さんとは180cm仲間の大きいちゃん倶楽部。丁度居合わせたつよちゃん鈴木強画伯と記念撮影。ニューヨークからは12日から銀座6丁目のギャラリー上田さんで個展の坂東優氏が来廊、こないだニューヨークでお世話になったばかりなのに、あの日がずいぶん前の事のよう。ご盛会を祈る。
夕方からはいつもの面々がぞくぞくと。りえぞー画伯の宇和島みやげの100円サングラスに大受けの小松謙一画伯に大爆笑!悦子のお鼻は同じくりえぞー画伯の伏見稲荷みやげ・商売繁盛まちがいなし!きつねのお面せんべい。ありがたくいただきましたぞ!
諏訪からは、御柱祭の法被をいなせに着込んだ、あずぴ旦那・ドクターみっちゃんが。Web大里氏は手づくりの手羽のコーラ煮を手にご来廊。16日から京王デパートで個展を控えたみそそ画伯の愛のお野菜をいただきながら今日のお幸せの画像を。
花の雨のラフティ亭にて
 生憎の花の雨ふる茅ヶ崎。二十数年ぶりに樋口薫画伯が七里が浜高校の同級生・小水氏と再会した。
生憎の花の雨ふる茅ヶ崎。二十数年ぶりに樋口薫画伯が七里が浜高校の同級生・小水氏と再会した。
実は小水氏、当地の池田美弥子画伯旦那・義孝氏とは中学の同期。その御縁で最近知り合ったのだが、樋口画伯の個展中同じ高校と判明、今日のご対面となった次第。
奥様の心尽くしの手料理と、シャンパーニュを手にした小水氏の歓迎を受け、樋口画伯、池田夫妻ともどもブラボーと叫ぶ。
アルバムを手に、高校時代を回顧する二人を後目に池田旦那と杯を重ねた悦子はもうお眠。旦那もまた撃沈、、。目覚めたその後は皆でしりとり俳句を作って終電まで遊ぶ。今日俳句デビューの四人、俳号は小水氏ーひろ、奥様ーごん、池田旦那ー多眠、美弥子ー海子、薫ー茶壷と相成った。先日デビューの武大人も含め、画壇句会を開くのも近い?
悦子の回りは花盛り!
斉藤典子展最終日ー時差ボケを越えて
 いつどこでも誰がいてもすぐ眠れる悦子と違ってデリケートな典子画伯、大事をとって夜遊びは控えていらしたが、今日は悦子宅にお泊まり。満開の桜に見送られて京都の展覧会へ。
いつどこでも誰がいてもすぐ眠れる悦子と違ってデリケートな典子画伯、大事をとって夜遊びは控えていらしたが、今日は悦子宅にお泊まり。満開の桜に見送られて京都の展覧会へ。
最終日は、いつも思いがけない方が見えるもの。今日は成城大学時代の恩師・田中日佐夫氏のご子息をお迎えした。やはり成城大で美術史を専攻した修二氏、今は大分大学で教鞭をとっている。
成城三年目にドイツに留学した典子画伯、トランクの中に田中先生の著作を入れていったという。その後何度も引っ越しする中、その著作だけは絶対手離なかったいきさつもあり、今日のご子息とのご対面には感無量。
成城の時には文化史を専攻、民俗学ゼミのお友達も北海道から来て下さり久々のミニ同級会に。お友達のお嬢さんは明日が大学の入学式という。18才だった日から幾星霜、同い年仲間の悦子も複雑な心境ながら
春になると青雲の志を思い出す。
そういえば、5年前ニューヨークで落ち合って3、4日過ごした折、
眠れないままホテルからセントラルパークまで歩き、お互いの来し方を話した事あったっけ。30年はあっという間だったが、時差ボケがホントのボケになるまでまだいくらか時間があるに違いない(もう十分ボケてる、という説も悦子の場合あるが)。まぁ行けることまで行ってみるか、まだ風も吹いてるようだし…。
願わくば、この種が出来るだけ遠くまで運ばれて、ちゃんと芽吹きますように!今日、その種を持ち帰ってくれた山本慎介さんと、悦子の戦友・七宝作家の黒田雅実ちゃん、秋田美人友の会々長ゆざわこまち佐藤友子女史とともに。
色彩学の権威・末長氏、ご夫妻で
青山で「ハート&カラー」という色彩学校を経営する末長蒼生氏と奥様の江崎泰子女史のご来廊。
ここでも何度も講座をもった典子画伯、先生たちの信頼も厚い。毎回作品を見ていただき、ご自宅を飾っていただいている作品も。色彩という側面から取り上げた、様々な分野の作家の御紹介をするギャラリーも併設、幅広い啓蒙活動をしておられる。
また、朝日カルチャーセンター横浜校の講座担当の石井洋子さんもご来廊。彼女は悦子の後輩・磯野ちゃんの同僚で、偶然にも以前にいらして下さったことが。今回はこちらで4月12、19、26日の三回授業をするとか。
アートセラピーというと、精神科医やサイコセラピストが分析などの一方法として治療や診断の手助けとして行うものと見られがちだが、一方では創作活動の体験やプロセスを通して自分の身体と心を癒すという方法が注目され、欧米では専門の勉強をしたアーティストがその任についているという。
ドイツで資格をとった典子画伯、日本では資格をとれる大学がなかったため末長氏とともに草分け的存在。この機会に興味のある方はどうぞ。詳しくはhttp://www.acc-web.com/yokohamaまで。
夜は、先日も御紹介したドクター山下の会員制ライブラリーで優雅なひとときを。六本木の街を下に見下ろしながら、天井まである本に興味津々の画伯たちのお姿を。
ところで、偶然居合わせた茅ヶ崎チーム。春彦さんと磯野ちゃんのお家はすぐ近所、池田美弥子画伯もその近くに最近まですんでいたとかで、こりゃまたローカルなお話に。
栃木県美術館の山本学芸員御登場!!
 昨日は葉山の神奈川近美参りとか、栃木の御縁で上京の山本和弘学芸員ご一行。3月21日まで栃美で開催の「DISTANCE Artists from Tochigi」に出展していた典子画伯に表敬を。
昨日は葉山の神奈川近美参りとか、栃木の御縁で上京の山本和弘学芸員ご一行。3月21日まで栃美で開催の「DISTANCE Artists from Tochigi」に出展していた典子画伯に表敬を。
郷里を離れている作家たち、ということだけでくくられた展覧会とのことで多種多様な作品がある中、9000kmの距離を経て展示された典子画伯の作品はどんな印象を故郷の人たちに与えたのだろうか。
画家にとって生地の影響は大きいものだが、離れて分かることもまた多い。犀星は「~遠くでおもうもの」と詩ったが、胸中の山河は消えることはあるまい。典子画伯の色もまた、、。
今日は陶芸の美崎氏はじめ筑摩書店の平賀氏、テリー&佐名ちゃん、大野麻子画伯などをむかえ楽しい一時を。
森恭ニ展ご紹介
二人で時差ボケ?
 おんや~?トシのせいか時差ぼけが直らず、二人で睡眠不足。典子画伯は、大事をとって早めにトロントを立って来たのに…。
おんや~?トシのせいか時差ぼけが直らず、二人で睡眠不足。典子画伯は、大事をとって早めにトロントを立って来たのに…。
とはいえ、一年ぶりの帰国にお待ちかねの方たちが引きも切らぬ画廊内、郷里足利から美術家の栃木美保女史をはじめ、アートセラピーの講座の生徒さんたちなどをお迎えする。
年に一度の展覧会の度、アートセラピストの草分け的な存在の彼女に講座の依頼が。ドイツでは癌患者の治療チームでセラピストとして働いていたことも。
彼女の絵の深い色をみていると、胸の奥から汲み上げている事がよくわかる。みつめているとどんどん色が湧き出てくるようだ。時差ぼけでよろよろしている悦子にとっては、ありがた~い作品たちである。
ご来廊の斉藤博美ちゃんや能島千晴ちゃんも一緒にうっとり…。
斉藤典子展初日ートロントより
 ニューヨークでは斉藤隆展が、そして東京の我が画廊ではトロント在住の画家・斉藤典子展が今日から。
ニューヨークでは斉藤隆展が、そして東京の我が画廊ではトロント在住の画家・斉藤典子展が今日から。
典子画伯は若く見えるが悦子と同い年の羊、しかもB型。なにか行動パターンがよく似ていて、さすらいの人生を送っている。とはいえ、画伯の方はアカデミック。
成城大で2年まで文化史を学んだ後、青雲の志のもとドイツに雄飛、以来20年近く彼地に。最初の大学ではフィールドワークを中心にした文化史と民俗学を、次のベルリン芸術大学ではアートを学んだのち、画家活動に入る。
シュタイナーやゲーテの色彩論に裏打ちされた彼女の絵画は、深い啓示を含んだ豊かな色味をもつ。ここ数年、「種子」をテーマに植物の生成の印象を描いて来たが、今展ではその種子が風に乗って着地する、その空気まで描きたくなったという。
どこに着地するか、そろそろ半世紀に近いそれぞれの人生にとっても大きなテーマだが、産土の闇から地表にでて、花咲き、実をつけ、また種子にもどり風に飛ばされ着地する、という植物の巡りはまた感興深い。
種の周辺に、大気と水の気配はつきもの。今回は雨後の日だまりのような情景として立ちあらわれて来た。カナダに移住して自然に触れ、植物の力に気付いたという画伯、部屋のなかから外へと彼女の「種子」たちも旅を始めたのだろう。
今日のお客人は、ドイツ時代の彼女を知るVip様、伊藤氏と半澤氏はじめ、画伯友人の由貴子さん、その御紹介の「福光屋」梁井氏など錚々たるメンバー。小河原ちゃんやニューヨークで知り合ったカウンセラーの田中さんもご一緒に。
最終日に間に合った!感激の大団円
 時差ぼけにつぐ時差ぼけの悦子、飛行機から降りたらへろへろ。三泊五日の間に何時間寝たやら。昨日、抱きつかんばかりに出迎えてくれた画伯と早苗ちゃんにスペシャルサンクスを!
時差ぼけにつぐ時差ぼけの悦子、飛行機から降りたらへろへろ。三泊五日の間に何時間寝たやら。昨日、抱きつかんばかりに出迎えてくれた画伯と早苗ちゃんにスペシャルサンクスを!
7日間の会期中のうち5日間、画廊を守ってくれた画伯たち、ちょっと見ないうちに一皮むけていた。精一杯やってくれていたのだろう、守りきった自信と喜びに満ちた二人を見て悦子も感無量。
京都で画伯の留守を守っていたご夫君・青山K一氏も今日は搬出のお役で上京。悦子の不在を不安がっていた画伯に「なんや、自分の個展やろ。柴田さんは画廊を存続させるためにいくんや。分かってあげなあかん」と行ってくれたのだと言う。まこと涙の出る台詞である。ご自身も昔人形青山というギャラリーを持ち、古人形とともに新作人形作家の御紹介もするご主人なだけに、悦子の心中をいわずもがなで察してくれたのだろう。
こういう有り難いサポートも含めて、仕事をさせていただいているお幸せ。時差ぼけなんていってる場合じゃない。
チベット・ネパールを一人で取材、かの地の生気を思う存分吸い込んで思う様描いた画伯。そのエネルギーが画廊中にあふれ、見ている人の顔を輝かしていく。堂々の画境だ。このままずんずん進んでいけばいい。童顔の彼女を見ていると、この無垢のままよく今まで生きてこれたと思う。だが、自分しかできないことをちゃんとしっている人だ。ますますの精進を願うものである。
本当に皆様ありがとうございました。
齋藤 隆展 in New York
 いよいよ今日はM.Y. Art Prospects URL/www.myartprospects.comにて齋藤隆展の初日。これから一か月展開される画伯の「墨聲紙韻」の世界がどんな反応をもたらすものか、お楽しみ。
いよいよ今日はM.Y. Art Prospects URL/www.myartprospects.comにて齋藤隆展の初日。これから一か月展開される画伯の「墨聲紙韻」の世界がどんな反応をもたらすものか、お楽しみ。
ニューヨークと東京の画廊同士の交流プログラムの一貫として企画された今展、齋藤隆画伯の十年に及ぶ墨との格闘を伝えるもの。
実は画伯、1970年初頭、デュシャンやダリとも交流のあったStaempfli gallery でN.Y.デビュー。今回は二回目の発表である。約30年の時を経て、大きく作風を変えた画伯ー同じ白と黒の表現ながら、かたや西洋紙にコンテ、こなた和紙に墨。かつてはグリューネバルトの祭壇画に心酔した画伯が、この歳月の間により東洋に心をよせ、住処とする福島の廃屋「風騒居」で紡いだものがこの度の一連の作品である。
生と死の葛藤は一見身を潜め、枯れ木や干された鮭の頭に象徴される「風化」へと姿をかえた。幾重にも張り合わされた和紙の上に丹念に描かれたそれら形象は、生から死への時間を内包し、我々の視線をさらに内側に向かわせる装置のようだ。彼の枯れ木を見ていると、あちら側に引き込まれて戻れなくなるような目眩すら覚えたものだ。
毛ほどもの弛みも許さない画伯の仕事は、さらに近年ストイックさを加え、美とグロテスクの境目さえ無くした。対比は内在され、耳を澄まし、目を凝らし、全身で感じとらないとまるで自然にさえ見える。
かつて異様とも鬼とも形容された画伯の世界は、墨との格闘を通して
深化し、「墨を選び、表現を支える衝動は確固としてあるのか」という自省とともに、墨の声を聞き紙の風韻を思う心境に到達したのだ、と思う。
日本の画壇によらず、僻村の人家すらない孤独な環境で、ただ好きなように酒を飲み山中の風光に暮らす、という浮き世離れは思ってもなかなかできるものではない。今回、作品をN.Y.にもってくるにあたっても画伯は画伯のお考えがあったと思う。
悦子と美也子女史の企てに賛同してくださった画伯と、所蔵の作品を一部提供してくれた富山・立山画廊主人堀實紀男氏に心からの感謝を!
さてオープニングは以下の如く盛況裡に。美也子女史ご夫君ジェフ氏も大活躍。また、おりから一年間N.Y.滞在中の内田あぐり画伯とも旧交を暖め言う事なし。里佳画伯は今日がお誕生日。ベリーショートでさらに若返り、少年のようなりりしさ。ネイティブたちの英語の海を、さも分かるように泳ぎながら、悦子は今日はサンローラン。頭には先日万里子ママからもらったマキシムのお帽子でオホホ。
美也子女史は、墨にあわせてグレーのドレスでエレガントに。ジェフからは、ノーブラで着るよう指示があったそうだが却下。う~ん残念!
その後は女ばかりで怪しいモロッコ料理の店で、水パイプなど堪能。楽しい夜となった。まずは三泊五日世界征服の旅ご紹介まで。もうすぐ帰るよ~!
ニューヨークは大雪!
 二年ぶりのニューヨークは大雪。前回の浅見貴子展は2001年と2002年を跨いで開催され、9.11の傷跡も生々しいN.Yを足早に歩いたものだったと思い出す。
二年ぶりのニューヨークは大雪。前回の浅見貴子展は2001年と2002年を跨いで開催され、9.11の傷跡も生々しいN.Yを足早に歩いたものだったと思い出す。
トランク一杯の斉藤隆画伯の絵を、ピックアップに来てくれた坂東優氏の車に積み込み、吉永美也子女史の待つ27丁目のM.Y Artまでドライブ。四月に銀座のギャラリー上田で個展予定の坂東氏、お忙しい中だったろうにと感謝!学校帰りの沙南ちゃんとママの里佳画伯とはアトリエで。里佳画伯の個展は今年九月、意欲的な新作を見せてもらう。
夜はカナダ・ビクトリアからわざわざ来てくれた沖縄出身ご存じ玉恵と娘のレイチェルと待ち合わせ、インド料理店でウェルカムパーティを。前回お知り合いになった、裏千家ニューヨーク支部長の山田先生と手織りのお店「八布」を営む植木たかこ女史がお友達を伴っていらしてくれた。なにを隠そう裏千家のニューヨーク支部というのは、マーク・ロスコの元アトリエ。その五階立てのビルをくり抜き、路地のある茶室を設えたという。マンハッタンのど真ん中に、それとはわからず和の空間を完璧に再現した山田先生はなんとも素敵なお方。お若い頃、建長寺の朝比奈宗源老師のご講話を同時通訳するのに苦労なさったという。今だったらもっと適当にできるのに、と呵々大笑。植木女史は日本の繭を使い手機で織る作家でもある。彼女の布はほとんど羽衣といっていい軽やかさで思わずすりすり。触る快楽を悦子に教えてくれた。
画廊のスタッフ・オードラーは芳紀19才。東洋宗教学を学ぶ彼女、真剣な目で展示を。いつのまにか25才になっていたレイチェル、実は30才だけど20代前半に見える裕子ちゃんという三人の小娘連合と、ちょうどこんな娘がいてもおかしくない悦子・美也子大娘連合プラス本物ママ玉恵の熟女組という、よりどりみどりの美女にさしもの山田先生も相好を崩す。な~んちゃって。
おりしも今日は聖パトリック・ディ。雪のセントラルパーク側をバグパイプ抱えて行進するアイリッシュたちを見ながら、抜かりなく五番街のテファニーをチェックする裕子お嬢の姿も御紹介。あ~悦子の指には大きいダイヤしか似合わないのが残念。
はじめてのお留守番ー悦子はN.Yへ
タシデレ竹内淳子展初日-淳子代筆
 タシデレ 今日からはじまりました、竹内淳子展、司会の竹内淳子です。2年ぶりのお目見えです。怒濤のように京都からやってきて、突入しております。一回目は悦子パワーに圧倒され、悦子画廊におとづれるパワーあふるる人々に圧倒され、アッというまに日々が過ぎていきましたが、まさか、悦子日記を書く事になろうとは、ココハ ドコ?ワタシハ ダレ?まさに、魔境、悦子画廊!おそるべし!!!さて、昨年10月にインド、ネパールに取材に行った折、チトワン公園という、野生動物保護区に脚を踏み入れました。その時偶然お知り合いになった、野口さん、サンケイの山と酒を愛する人々をヤマホド引き連れて来て下さいました。そのメンバーの田中さんは、昔から悦子サマのヤマの友だそうな、、、どうして、ここで、つながるのか?悦子マジック。安住画伯と将来音楽家の凛々しいお嬢様おいでいただきました。ご夫婦ともに悦子画廊のナビゲーター?小黒さま、皆様ご出演有り難うございます。夕方ともなると、司会者の昔仲間、ライター渋谷氏、絵地図作家谷口氏、シルクスクリーン作家佐藤氏、イラストレーター佐藤氏、ミャンマー写真家後藤氏、インド写真家柴田氏が駆け付けて下さいました。そして、なんとカブリモノ大会に突入!これは、悦子画廊のみせる幻か、羊アタマ、牛頭、アヒル頭、マキシムまで出て来た、そして、悦子動物園の禁断の夜はフケテいくのでした、、、ツヅク、、、、
タシデレ 今日からはじまりました、竹内淳子展、司会の竹内淳子です。2年ぶりのお目見えです。怒濤のように京都からやってきて、突入しております。一回目は悦子パワーに圧倒され、悦子画廊におとづれるパワーあふるる人々に圧倒され、アッというまに日々が過ぎていきましたが、まさか、悦子日記を書く事になろうとは、ココハ ドコ?ワタシハ ダレ?まさに、魔境、悦子画廊!おそるべし!!!さて、昨年10月にインド、ネパールに取材に行った折、チトワン公園という、野生動物保護区に脚を踏み入れました。その時偶然お知り合いになった、野口さん、サンケイの山と酒を愛する人々をヤマホド引き連れて来て下さいました。そのメンバーの田中さんは、昔から悦子サマのヤマの友だそうな、、、どうして、ここで、つながるのか?悦子マジック。安住画伯と将来音楽家の凛々しいお嬢様おいでいただきました。ご夫婦ともに悦子画廊のナビゲーター?小黒さま、皆様ご出演有り難うございます。夕方ともなると、司会者の昔仲間、ライター渋谷氏、絵地図作家谷口氏、シルクスクリーン作家佐藤氏、イラストレーター佐藤氏、ミャンマー写真家後藤氏、インド写真家柴田氏が駆け付けて下さいました。そして、なんとカブリモノ大会に突入!これは、悦子画廊のみせる幻か、羊アタマ、牛頭、アヒル頭、マキシムまで出て来た、そして、悦子動物園の禁断の夜はフケテいくのでした、、、ツヅク、、、、
タシデレ竹内淳子展初日-淳子代筆
 タシデレ 今日からはじまりました、竹内淳子展、司会の竹内淳子です。2年ぶりのお目見えです。怒濤のように京都からやってきて、突入しております。一回目は悦子パワーに圧倒され、悦子画廊におとづれるパワーあふるる人々に圧倒され、アッというまに日々が過ぎていきましたが、まさか、悦子日記を書く事になろうとは、ココハ ドコ?ワタシハ ダレ?まさに、魔境、悦子画廊!おそるべし!!!さて、昨年10月にインド、ネパールに取材に行った折、チトワン公園という、野生動物保護区に脚を踏み入れました。その時偶然お知り合いになった、野口さん、サンケイの山と酒を愛する人々をヤマホド引き連れて来て下さいました。そのメンバーの田中さんは、昔から悦子サマのヤマの友だそうな、、、どうして、ここで、つながるのか?悦子マジック。安住画伯と将来音楽家の凛々しいお嬢様おいでいただきました。ご夫婦ともに悦子画廊のナビゲーター?小黒さま、皆様ご出演有り難うございます。夕方ともなると、司会者の昔仲間、ライター渋谷氏、絵地図作家谷口氏、シルクスクリーン作家佐藤氏、イラストレーター佐藤氏、ミャンマー写真家後藤氏、インド写真家柴田氏が駆け付けて下さいました。そして、なんとカブリモノ大会に突入!これは、悦子画廊のみせる幻か、羊アタマ、牛頭、アヒル頭、マキシムまで出て来た、そして、悦子動物園の禁断の夜はフケテいくのでした、、、ツヅク、、、、
タシデレ 今日からはじまりました、竹内淳子展、司会の竹内淳子です。2年ぶりのお目見えです。怒濤のように京都からやってきて、突入しております。一回目は悦子パワーに圧倒され、悦子画廊におとづれるパワーあふるる人々に圧倒され、アッというまに日々が過ぎていきましたが、まさか、悦子日記を書く事になろうとは、ココハ ドコ?ワタシハ ダレ?まさに、魔境、悦子画廊!おそるべし!!!さて、昨年10月にインド、ネパールに取材に行った折、チトワン公園という、野生動物保護区に脚を踏み入れました。その時偶然お知り合いになった、野口さん、サンケイの山と酒を愛する人々をヤマホド引き連れて来て下さいました。そのメンバーの田中さんは、昔から悦子サマのヤマの友だそうな、、、どうして、ここで、つながるのか?悦子マジック。安住画伯と将来音楽家の凛々しいお嬢様おいでいただきました。ご夫婦ともに悦子画廊のナビゲーター?小黒さま、皆様ご出演有り難うございます。夕方ともなると、司会者の昔仲間、ライター渋谷氏、絵地図作家谷口氏、シルクスクリーン作家佐藤氏、イラストレーター佐藤氏、ミャンマー写真家後藤氏、インド写真家柴田氏が駆け付けて下さいました。そして、なんとカブリモノ大会に突入!これは、悦子画廊のみせる幻か、羊アタマ、牛頭、アヒル頭、マキシムまで出て来た、そして、悦子動物園の禁断の夜はフケテいくのでした、、、ツヅク、、、、
首里の昼、那覇の夜
 樋口展終了後、早速次の作戦開始。かねて懇意の陸奥男山酒造御曹子
樋口展終了後、早速次の作戦開始。かねて懇意の陸奥男山酒造御曹子
駒井秀介氏の御紹介を受けて営業先にご挨拶を。若旦那のりりしく立ち働く姿に感銘をうけつつ、担当の方に繋いでもらう。
色々なところに御縁はあるもの、今回は首里でご自分のギャラリーを営む仲本京子さんという画家の方に巡り会った。なんと悦部屋を二年前から覗いてくれていたという。あなたが柴田さんですか、といわれると「すみません、こういうやつでした」と思わずあやまってしまうリアクションが我ながら恥ずかしい。
仲本画伯は、沖縄とニューヨークで個展を重ねているバイタリティあふれるお方。南国の底抜けに明るい色調の絵を拝見しながら、彼女のキュートなお人柄に魅了される。かたわらにはダンディなご夫君が控えられ暖かくむかえてくださったのも有り難いこと。
いつもエネルギーをくれるこの島の、ネイティブが描いた沖縄の絵は、ナイーブアートの枠を越えて新鮮な驚きをもたらしてくれた。来週のニューヨーク行きをつたえたら、MY art prospectsにも行った事があるという。まったく世間は狭い。
沖展で浦添市長賞を受賞した宮城忍君に向かえに来てもらって、首里そばの美味しい店でお昼を堪能。さすが首里だけあって上品この上ないお味、店の名は、、う~んと、なんとかギャラリー。とにかくお勧め。
宮城くんのアトリエっで打ち合わせ後、宮城パパの経営する「マルメロ」というケーキ屋さんでニューヨークにおみやげにするバナナケーキを注文。これがまたうまい!
夜はかの大城美佐子先生の民謡酒場「島想い」で歌と踊りを。嘉手刈林昌先生の思い出話などしみじみ拝聴する。沖縄はへのこという所ご出身の大城先生、その頃は女がサンシンをもつだけでオバアたちの顰蹙をかったという。彼女の激動の人生をちと垣間みて、歌がなおさら胸にしみた。
仲本さんにしろ、大城先生にしろ、このような魅惑的な女たちが今も生きる沖縄。そのやさしさとパワーに今回もなにか励まされた想いで、島を後にした悦子だった。
ハンサム樋口画伯最終日
 連日のお客様を、華麗なるフットワークでお持てなしつつ、いよいよ大団円の今日は明石から橘万里子ママが。
連日のお客様を、華麗なるフットワークでお持てなしつつ、いよいよ大団円の今日は明石から橘万里子ママが。
悦子も今日は朝から大忙し。適切なハンサム君のサポートを受けつつ、各種仕事を。
一息ついて、万里子ママのご友人・築地の鮭問屋さんの若奥様よしみさんとお嬢様の早絵ちゃんとお茶っこ。ママからは神戸マキシムのお高い万円お帽子をいっぱい頂く。帽子なくしては語れぬ悦子にとって、塩辛い鮭の皮とともにうれしいプレゼント。
来週は橘家の令嬢・裕子ちゃんとニューヨーク行きの悦子、どの帽子でいこうかな。
ちょうど、いらした武田州左画伯は樋口画伯が美大一年の時の四年生、悦子の一年下の学年にあたる。二人目のお子さんが夏誕生予定との事で、なにより。万里子ママにご紹介できてよかった、よかった!
後ろのかっこいいガイは画伯のサーファー友達。そういえば裕子ちゃんもハワイにサーファーの友達が一杯の筈。ご縁がまたあるといいな。
てな事で盛り沢山の今展、画伯の新境地に驚く皆様を横目にみつつ悦子的には大満足。一歩踏み出した樋口画伯の意欲を高く買い、プロへの一里塚をクリアしたとして評価したいと思う。これからどんどん増えるハードルを、果敢に乗り越えて欲しいと祈るや切。
ご来廊の皆様、ありがとうございました。樋口画伯に更なるご声援を!
Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20




